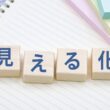電気とガスをバランスよく使う暮らし方とメリット

家のエネルギー設計を考えるとき、多くの人が「オール電化か、それとも電気とガスの併用か」という選択肢に直面します。
近年は電気料金の高騰や太陽光パネルの普及に伴い、オール電化の魅力が語られることが多いですが、電気とガスをバランスよく使う「ハイブリッド型」の暮らしにも大きな価値があります。
特に、災害時のリスク分散や生活の快適性、料金の安定性といった視点から見ると、電気+ガス併用は非常に柔軟な選択肢です。この記事では、その特徴や導入のポイントを詳しく解説します。
電気+ガス併用の3つのメリット
1. 災害時のリスクヘッジ
停電時にはIH調理器や電気給湯器が使えなくなりますが、都市ガスやプロパンガスを併用していれば、ガスコンロやガス給湯が稼働できる場合があります。
地域や設備によってはガスの復旧が電気より早いケースもあり、非常時に強い備えとなります。
2. 生活の快適性
ガス給湯はお湯が出るまでの時間が短く、シャワーや浴槽の使い勝手が良好です。
また、料理好きの方には、火力調整の幅が広く直火調理が可能なガスコンロは大きな魅力となります。一方、電気家電の便利さやクリーンな調理環境も享受でき、双方の長所を組み合わせられます。
3. 料金の安定性
電気・ガスそれぞれの料金は燃料価格や市場の影響を受けますが、併用することで一方の料金が高騰しても影響を抑えられる可能性があります。
主な組み合わせ例
- 太陽光+ガス給湯+IH調理
日中は太陽光発電で電力をまかない、給湯はガスで行うパターン。災害時にはガスが使えるため安心感があります。 - 太陽光+ガスコンロ+電気給湯
調理はガスで、給湯はエコキュートなどの電気給湯器を使用。夜間の安い電力を活用できる時間帯別料金プランとの相性が良い組み合わせです。 - 都市ガス+エコキュート+IH
ガス暖房やガスファンヒーターを併用しながら、調理はIHで行うスタイル。ガスと電気のいいとこ取りが可能です。
コスト面の考え方
電気とガスを併用すると、両方の基本料金が発生します。そのため、固定費はオール電化よりやや高くなることがあります。
しかし、ガス給湯器はエコキュートなどの電気給湯器に比べて導入コストが安く、寿命も長め(約10〜15年)です。また、電気料金が高いときはガスの使用を増やす、ガス代が高いときは電気を活用するなど、運用面での調整が可能です。
災害・停電時の活用例
- 調理:ガスコンロは停電時でも使用可能(ガス給湯器は点火用の電力が必要ですが、ポータブル電源で対応可能な機種もあり)
- 暖房:ガスファンヒーターは短時間で部屋を温められるため、冬の停電時に心強い存在
- プロパンガス:地域によってはタンクに数週間分のガスを備蓄している場合もあり、長期停電時に役立ちます
セット割引でお得に
多くの電力会社やガス会社では、電気とガスを同じ事業者で契約する「セット割」を用意しています。
例として、東京ガスでは「電気・ガスセット割」で月額110〜220円の割引があります(条件や契約容量による)。こうした割引を活用すれば、併用型の固定費増加分をある程度抑えられます。
選び方のポイント
- ライフスタイル:在宅時間が長い家庭では、時間帯別料金プランや太陽光発電との組み合わせが有効
- 地域特性:都市ガスかプロパンか、地震や台風などの災害リスクも考慮
- 太陽光発電の有無:自家消費とガスの組み合わせは効率的
- 契約プランやセット割の有無:割引をうまく使ってコストを抑える
- 設備更新時期:給湯器やコンロの交換タイミングで見直すとスムーズ
まとめ
電気とガスの併用は、コストの安さだけを追求するなら不利に見えるかもしれません。
しかし、災害への備え、快適性、料金変動への耐性といった点で非常に強いバランス型の選択肢です。特に太陽光発電との組み合わせは、自家消費とガスの相互補完により、家庭のエネルギー自立度を高めることができます。
「オール電化か、それとも併用か」という二択ではなく、自分の地域特性や生活スタイルに合った形でエネルギーを組み合わせることが、長期的に見て賢い選択といえるでしょう。