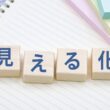待機電力とは?電気代に影響する「見えないコスト」の正体

使っていないのに電気代がかかる?
日常生活で家電を使っていないはずなのに、電気代が思ったより高い…。そんなときに見落とされがちなのが「待機電力」です。
待機電力とは、電化製品の電源を入れていない状態でも、コンセントに差しっぱなしで消費されている電力のこと。わずかな量とはいえ、24時間365日かかり続けるため、家計に与える影響は決して小さくありません。
待機電力は家庭全体の5%前後を占める
資源エネルギー庁の推計によれば、一般家庭における電気の使用量のうち、約5.1%が待機電力によるものとされています。
これは、年間約228kWhに相当し、電気代に換算するとおよそ年間7,000円弱。家族で外食1回分くらいの金額が、知らないうちに消えているということになります。
さらに、家庭によっては待機電力の比率が10%を超えるケースもあるため、侮れません。
昔に比べて家電の待機電力は大幅に減っている
とはいえ、すべての家電が同じように待機電力を消費しているわけではありません。技術の進歩により、最新の家電製品では待機電力が大幅に抑えられているものもあります。
たとえば、家庭での電力使用量の大きな割合を占める冷蔵庫やエアコンなどは、省エネ性能の向上により、過去10年で消費電力が大きく削減されています。特に冷蔵庫は約40%以上の省エネが進み、待機電力も最小限になっているものが増えています。
また、ドライヤーや電気ポット、炊飯器などの中には、待機電力がほとんど発生しないタイプもあります。
どんな家電が待機電力を消費しやすい?
待機電力を消費する家電の特徴としては、以下のようなものが挙げられます。
- リモコン操作が可能な機器(テレビ、エアコンなど)
- タイマー機能付きの家電(炊飯器、電子レンジ)
- 時計や表示ランプが常時点灯している機器(ビデオデッキ、Wi-Fiルーター)
- コンセントに接続しただけでスタンバイ状態になる機器
- これらは使っていない時間帯でも微量の電力を消費し続けており、塵も積もれば…の典型例です。
家電によってはコンセントを抜かなくてもOKな場合も
待機電力=すべての電化製品が悪者、というわけではありません。
たとえば、最新のテレビは、待機電力が1W未満に抑えられている機種もあり、節電目的でいちいちコンセントを抜く必要はないケースもあります。
逆に、古い家電は10W前後の待機電力を持つものもあり、対策の優先順位を考えることが重要です。
まとめ
待機電力は、電気を「使っていないときにかかっているコスト」であり、毎月の電気代にじわじわと影響しています。
ただし、すべての家電が対象ではなく、年々省エネが進んでいるのも事実。まずは「どの家電がどれくらい待機電力を使っているか」を知ることが、最初の一歩になります。
具体的な対策や、どうやって待機電力を抑えるか、どんな家電の買い替えが有効かは、別の記事で詳しくご紹介します。